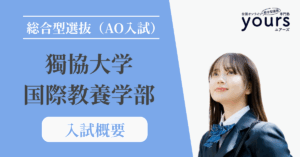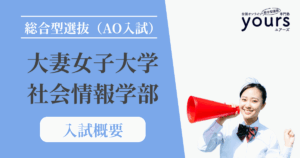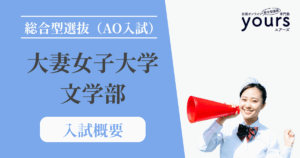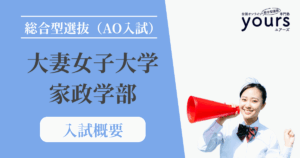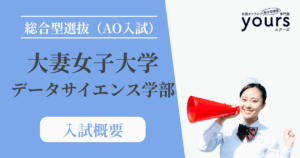近畿大学 工学部 総合型選抜の入試概要
| 学部(募集要項) | 工学部 | ||||||
| 学科 | 化学生命工学科 | 機械工学科 | ロボティクス学科 | 電子情報工学科 | 情報学科 | 建築学科 | |
| コース等 | |||||||
| 入試方式 | |||||||
| 詳細な方式 | |||||||
| 募集人数 | 40人(全学科合計) | ||||||
| 出願資格 | 評定 | ||||||
| 外国語資格 | |||||||
| 専願 | |||||||
| その他 | 数学の基礎学力を有すること。 生物、化学に興味、探究心があり意欲的に学ぶ強い意志があること。 | 数学の基礎学力を有すること。 物理、数学分野において理解力・考察力があること。機械工学を学ぶ意欲と自己の将来像や夢が明確であること。 | 数学の基礎学力を有すること。 ロボットおよび関連分野に強い探究心を持っていること。 | 数学の基礎学力を有すること。 電子や情報の技術に関連する話題において、相手の話を聞き取り、自己の意見を表現するコミュニケーション能力があること。 | 数学の基礎学力を有すること。 情報技術の基礎的事項に対する理解力があること。情報技術を学ぶ動機・意欲と探究心を持ち、自己の将来像が明確であること。 | 数学の基礎学力を有すること。 建築、インテリアデザインに興味があり、積極的かつ意欲的に取り組む姿勢があること。 | |
| 出願資料 | 入学志願書 | ||||||
| 志望理由書 | ○ | ||||||
| エントリーシート | |||||||
| 推薦書 | |||||||
| 自己推薦書 | |||||||
| 活動報告 | ○ | ||||||
| 調査書 | ○ | ||||||
| 外国語資格 | |||||||
| その他 | 資格・検定試験の取得を示す資料(写)(任意) | ||||||
| 試験内容 | 面接 | ○ | |||||
| 小論文 | |||||||
| プレゼン | |||||||
| GD | |||||||
| 外国語試験 | |||||||
| 筆記試験 | ○ | ||||||
| その他 | 筆記試験の出題範囲:「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B(数列)」 | ||||||
| 出願期間 | 9/19-10/1 | ||||||
| 試験日 | 10/18 | ||||||
近畿大学の概要
建学の精神
実学教育と人格の陶冶
真の「実学」とは、必ずしも直接的な有用性を志向するだけではなく、その事柄の意味を学び取ることを含む。現実に立脚しつつも、歴史的展望をもち、地に足をつけて、しなやかな批判精神やチャレンジ精神を発揮できる、創造性豊かな人格の陶冶を志向するものである。
沿革
近畿大学は、1925年(大正14年)創立の大阪専門学校と、1943年(昭和18年)創立の大阪理工科大学を母体とし、1949年(昭和24年)の新学制により設立された私立総合大学である。
創設者であり初代総長の世耕弘一は、「実学教育」と「人格の陶冶」を建学の精神とし、「人に愛される人、信頼される人、尊敬される人の育成」を教育理念に掲げた。世耕は、自らの苦学の経験と政治家としての歩みを経て、「すべての日本人に高等教育の機会を」という理想のもと、総合大学としての近畿大学の礎を築いた。
1949年の設立当初は理工学部と商学部を設置し、その後も順次学部を増設。1950年に法学部と短期大学部、1954年に薬学部、1957年に通信教育部、1958年に農学部、1959年に工学部、1966年に第二工学部(現・産業理工学部)、1974年に医学部、1989年に文芸学部、1993年に生物理工学部、2010年に総合社会学部、2011年に建築学部、2016年に国際学部、2022年に情報学部を開設し、発展を続けてきた。
現在では、15学部49学科、大学院11研究科・1学位プログラムを有し、17の研究所、2つの短期大学部、18の併設校園、2つの総合病院を設置するなど、日本屈指の私立総合大学に成長している。学生数は約3万人、卒業生は55万人を超え、各界で活躍している。2025年には創立100周年を迎えるに至った。
教育の目的
創立者である世耕弘一が唱えていた、「人に愛される人、信頼される人、尊敬される人の育成」を、そのまま教育の目的としている。
近畿大学 工学部の学部概要
特色
■化学生命工学科
◇学際的な3つの専門コース
3年次から以下のコースを選択し、専門的な知識と技術を修得する。
・化学・生命工学コース:化学と生物学を複合的に学び、幅広い応用力を養成。
・環境・情報化学コース:化学、生物、環境、情報技術を統合的に学習し、低炭素社会への貢献を目指す。
・医・食・住化学コース:医薬品、食品、建材など生活に密接した分野の化学を深く学ぶ。
◇情報処理技術の基礎教育
全コース共通で、化学メーカーや製薬メーカーでのデジタル化に対応できるよう、情報処理技術の基礎と応用力を身につけるカリキュラムを提供。
◇持続可能な社会への貢献
化学、生物学、環境、情報技術を活用し、持続可能な社会の実現に貢献できる技術者の育成を目指す。
■機械工学科
◇基幹6分野を中心とした実践的な教育
「材料力学」「機械力学」「熱力学」「流体力学」「材料工学」「制御工学」の6分野を基礎とし、講義・演習・実験を通じて実践的な設計能力を養成する。
◇2つの専門コースによる専門性の深化
2年次から「機械設計コース」と「エネルギー機械コース」に分かれ、各分野での専門知識と技術を深める。
・機械設計コース:機械の構造や強度設計、加工技術、CADを用いた設計手法を学び、実践的なスキルを修得する。
・エネルギー機械コース:エネルギー変換技術や流体力学、熱力学、機械を効率的に動かすための最適なエネルギー供給方法について学ぶ。
◇設計製図能力の重視
手書きから3D-CADによる製図まで一貫した技術を身につけ、機械工学を駆使した設計能力を養う。
◇JABEE認定による国際的な技術者教育
国際的な技術者共通資格であるJABEE認定のカリキュラムを採用し、国際的に通用する機械技術者を育成する。
■ロボティクス学科
◇機械・情報・電気電子の融合教育
ロボット製作を通じて、機械、情報、電気電子の複合技術を学び、メカトロニクス技術者を目指す。
◇2つの専門コースでの学び
2年次から「ロボット設計コース」と「ロボット制御コース」に分かれ、専門的な知識と技術を修得する。
・ロボット設計コース:機構学、設計工学、加工工学などを学び、創造的な設計力と企画力を養う。
・ロボット制御コース:制御工学、情報工学などを学び、ロボットの知能化に必要な応用力を身につける。
◇幅広い分野での応用
製造業だけでなく、福祉や医療など多様な分野で活躍できるロボット技術を学ぶ。
■電子情報工学科
◇ハードウェアとソフトウェアの融合教育
電子回路や半導体、電力システムなどのハードウェア技術と、ネットワークや通信システム、ソフトウェア工学などのソフトウェア技術を統合的に学び、ICTスペシャリストを育成する。
◇2つの専門コースでの学び
2年次から「電気電子コース」と「情報通信コース」に分かれ、専門的な知識と技術を修得する。
・電気電子コース:電子回路、エネルギー変換工学、パワーエレクトロニクスなどを学び、エレクトロニクス分野で活躍できる技術者を育成する。
・情報通信コース:プログラミング、ネットワーク、データベース、人工知能、画像処理工学などを学び、高度な情報技術を備えたエンジニアを育成する。
◇実践的な教育と研究
実験や実習を通じて、理論だけでなく実践的なスキルを身につけ、即戦力となるエンジニアを目指す。
■情報学科
◇情報技術の基礎から応用まで体系的に学習
プログラミング、アルゴリズム、データベース、ネットワーク、人工知能など、情報工学の基礎から応用までを体系的に学ぶ。
◇実践的な教育と研究
実験やプロジェクトを通じて、理論だけでなく実践的なスキルを身につけ、即戦力となるエンジニアを目指す。
◇多様な進路への対応
IT企業、製造業、通信業など、幅広い分野での活躍が期待される。
■建築学科
◇実践的な建築教育と資格取得支援
建築の設計、構造、環境、歴史などの基礎から応用までを体系的に学び、一級建築士や二級建築士などの資格取得を目指す。
◇2つの専門コースによる専門性の深化
2年次から「建築学コース」と「インテリアデザインコース」に分かれ、各分野での専門知識と技術を深める。
近大
・建築学コース:建築物の構造や環境への配慮を学び、安全性と機能性を備えた設計技術を修得する。
・インテリアデザインコース:空間デザインや照明・家具の配置、色彩計画を学び、快適で魅力的な空間を創造する技術を身につける。
近大
◇JABEE認定による国際的な技術者教育
国際的な技術者共通資格であるJABEE認定のカリキュラムを採用し、国際的に通用する建築技術者を育成する。
◇多様な進路への対応
建築・住宅関連企業、設計事務所、建設会社、インテリアデザイン関連企業など、幅広い分野での活躍が期待される。
アドミッション・ポリシー
①工学部での学修に必要な基礎学力を有し、旺盛な学修意欲のある人。
②社会における互いの多様な価値観を理解し、これらを尊重することのできる倫理観のある人。
③自然との共生の大切さを理解し、社会に貢献できる新たな技術を創造しようとするチャレンジ精神のある人。
④国際的な視点に立って行動しようとする意欲のある人。
キャンパス
広島キャンパス(工学部)
〒739-2116 広島県東広島市高屋うめの辺1
教育研究上の目的・ポリシー
工学部の教育研究上の目的はこちら
学生数
2,288人(2024年現在)
特色
化学生命工学科の特色はこちら
機械工学科の特色はこちら
ロボティクス学科の特色はこちら
電子情報工学科の特色はこちら
情報学科の特色はこちら
建築学科の特色はこちら